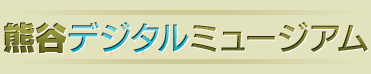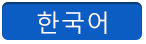中山道と史跡・文化財
23.志がらき茶屋本陣跡(明治天皇御小休所跡)
|
江戸時代、中山道を行き来する大名や幕府公用者に、お茶や食事を提供した休憩所。宿泊施設ではない。当時、くまがやの名物は「しがらきごぼうに久下ゆべし」といわれていました。
『中山道道中商人鑑』(文政8年:1825)に「中山道籠原 御茶漬 名物牛蒡あり 梅ひしは 御土産曲もの入 諸国御大名様方 御小休 江戸ヨリ左側 京都ヨリ右側 しがらきノ 笹屋源蔵 籠原中程にて」と紹介されています。 『五街道中細見記』(安政5年:1858)には「御殿家」と記載されています。 また、文久元年(1861)11月12日には、仁孝天皇の第8皇女和宮(1846-1877)が徳川14代将軍家茂(1846-1866)に御降嫁道中の際、ここで小休止し、熊谷本陣に宿泊しています(和宮御休泊日割)。 明治11年9月2日、明治天皇が北陸・東海両道を巡行した際、小休止し、埼玉県指定旧跡となっています。昭和13年には「明治天皇御小休所趾」の石碑が建てられています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『島根のすさみ』に記載されている籠原の茶屋(しがらき茶屋)の記述を紹介します。この日記は、天保11年(1840)、幕府勘定吟味役の川路聖謨(としあきら:1801-1868)が、佐渡奉行所の腐敗を一掃するために佐渡奉行に抜擢され、江戸から中山道を通り三国峠、寺泊を経由して佐渡に渡り、再び江戸に戻るまでの日々を記したものです。 「島根」は佐渡相川、「すさみ」は心に浮かんだあれこれということです。 天保11年(1840)7月11日に江戸を発ち、7月12日には上尾から本庄まで進んでおり、途中籠原で小休止しており、様子を記しています。 「籠原の建場にて従者の物語を聞に ここの牛房の味ことによしといふ故 障子の破よりうかがひみしに白き飯にそへて物する様いかにも味あるかことくにみゆ よつて密に申して某か如くにはせて一椀をとりよせものせしに いかにも味あり 飯二椀をものしぬこのことのなからましかは けふは飢可申によき序にそありけるされと又一笑の事也 ここにて梅ひしほのうちにはしかみを薄くきりて加たり 甚よし 作りて母上に奉るへし 紫蘇の実をも少々加へたると覚ゆる也」 籠原の茶屋で食べたごぼうが、ご飯を2杯も食べるほどおいしかったと記しています。「梅ひしお」は、梅干しで作った万能調味料です。 【参考】 川路聖謨・川田貞夫『島根のすさみ』佐渡奉行在勤日記 東洋文庫226 1973年 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
弘化4年(1847)に、一筆庵主人が書いた『魂膽夢助譚』(こんたんゆめすけばなし)で熊谷の様子が書かれていますので紹介します。概要:夢輔という怠け者が、金に不自由なく、長生きして遊んで暮らすには、信心願かけでご利益を得るのが近道と考え、七福神の中でも一番暇そうな福禄寿にお願いした。すると福禄寿から、ある生き物をみつめて呪文を唱えると、その生き物と魂が入れ替わるという術を伝授された。 ある時、夢輔と粟九郎は、叔母の遺金二百両を貰うために、上州二連木に向けて出立する。板橋の宿より中山道を通って上州に至る途中、熊谷に立ち寄っています。 「夢輔譚 五編 下の巻」 (前略) ゆめ「ここが久下村といふ所で、茶漬の名物だ。 あは「酒のいい所で、一口呑で急ふ。 ゆめ「それじやア熊谷の和泉やだト。 二人は道をいそぎしかば、ほどなくくまがやへの宿にいたり、いづみやにてそこそこに酒をのみ、蓮生寺もけへりに参けいせんと、心いそがはしく、此宿も通りすぎ、はやくも駕原の立場にいたる。この所は、熊谷、深谷の間にて、しがらきといふ立場茶やは牛蒡(ごぼう)のめいぶつ也。殊に自製の茶は当所の水にあひて風味よく、旅人茶をもとめていへづとになす。銘をしがらきとよべり。煮花に牛蒡ふたきれにて、茶づけめしを売といへども、其繁昌は中山道第一の立場にて、旅人ここにあらそひ休みこんさつす。 ゆめ「ここで飯を喰て行ふ。 あは「なんだ茶漬か。 ゆめ「ムム酒も肴も銭さへ出せばお望次第ヨト。 こしをかける。女茶を持くる。 あは「酒なしの飯がいい。 ゆめ「わるツくツても仕かたがねへト。 いふ内二人まへ茶づけを持てくる。二人はまじめにめしをくひ、 ゆめ「どうも茶はよつぼどいいぜ。 あは「山本山でも怊(かな)はねエなアト。 茶づけをくひながら、 「熊谷の和泉やも酒はいいが、夕べの吹上の酒はよツぽどよかった。 ゆめ「そのはづだア。壱両壱分取れたものを惚きって夜這に行ほどだから、能なくつちやア妻らねエ。 (後略) *立場(たてば)とは、宿場と宿場の間にあって、旅人が休息する場所の事で、熊谷宿と深谷宿の間の籠原に、牛蒡と茶漬けが名物の「しがらき」という店があった。 *作者の「一筆葊」とは、「岐阻道中熊谷宿八丁堤景」を描いた、絵師で文筆家の溪斎英泉の亭号 【参考】 『魂膽夢助譚』横山芳郎 平成8年 ㈱考古堂書店 |
|---|
 |
より大きな地図で 中山道をめぐる熊谷の歴史と文化財 を表示 |